やー! たぬだよー!
みんなも心に残る作品の100、200あると思うの!
今日はたぬたぬらんどのみんなで、そんな心に残る一冊を
やってみるのー!
つまり……!
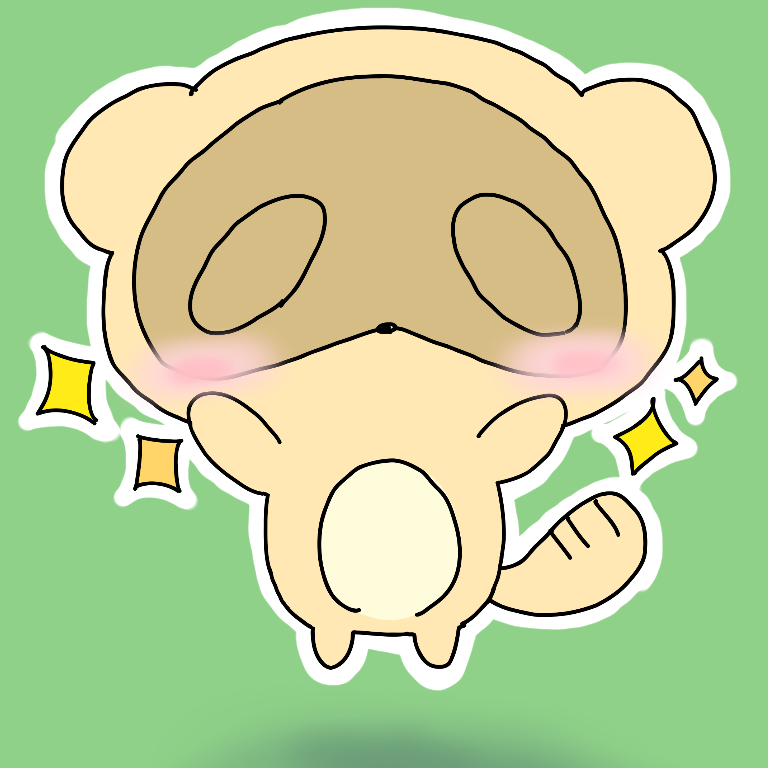
たぬたぬらんどがー!

山月記をやってみたのー!
- 山月記と聞いて少年の心が疼くお友達
- 中島 敦先生の文章がとにかく好きだ! のお友達
- たぬたぬらんどのお友達!
それでは、やっていきましょー!
中島 敦先生とは
東京に生れる。東京帝国大学国文科卒。横浜高女で教壇に立つ。宿痾の喘息と闘いながら習作を重ね、1934年、「虎狩」が雑誌の新人特集号の佳作に入る。’41年、南洋庁国語教科書編集書記としてパラオに赴任中「山月記」を収めた『古譚』を刊行、次いで「光と風と夢」が芥川賞候補となった。’42年、南洋庁を辞し、創作に専念しようとしたが、急逝。「弟子」「李陵」等の代表作の多くは死後に発表され、その格調高い芸術性が遅まきながら脚光を浴びた。享年33。
中島 敦著『李陵・山月記』株式会社新潮社 昭和四十四.カバー著者紹介より
中島 敦先生との出会いは、たぬがスタンドカラアのシャツと袴姿で、学問を修めていた頃だったの。
一文字も揺るがせにできない文章に、夢中になって読み耽ったの。
たぬも多大な影響を受けたの。山月記、李陵、名人伝、光と風と夢など作品の数こそ少ないけど熱中したの!
『山月記』は中島 敦先生の代表作で国語の教科書にも、登場するくらい人気なの。知ってる人もいると思うの。
今日はそんな『山月記』のパロディをやってみるのー!
3・2・1 アクションスタート!
神武以来の阿呆

筑紫州にて、たぬというものあり。
物書けぬ物書きとして、その悪名は山々に轟き渡っていた。
思い乱れ、筆は遅々として進まぬ。筆を手にすることすら、本能が拒絶しているかのようであった。
そのくせ、倨傲で大上段から言うことは役者の如き口上をツラツラと述べるから質が悪かった。
「あめのした、何事もなさぬにはあまりに広いが、何事かをなすにはあまりに狭い」というのが、このたぬの口癖であった。
どうやら、本気で己のことを神武以来の文士であると思っているらしい。
到頭、妄想が脳内だけでは収まりがつかなくなったらしいと見え
己が一文字として書けぬ才覚に、満腔の自信をもって故山、たぬき山に帰臥した。
彼が何を担保に、その自信を得、保持し続けたか知るものは未だいない。
去り際、彼が傍輩に残したセリフはあまりに有名である。
「諸君らはそのまま平々凡々と勤め果せるがよい。たぬは己がなすべきことをなし名を死後、百年は残してくれる!」
このあまりに驕り高ぶった一文は、今なお彼が勤めた部署に残っている。
無論、伝説のお笑い種として……。
しかし、文名は容易に揚がらず。そもそも一文一文字書いてないのだから揚がる名もなく、生活は困窮を窮め、その容貌も日に日に峭刻となっていた。己を恃むことに一片の躊躇いもなかった気持ちにも、多少、否。
多分に陰りが見え始めてきた頃であった。
かつて彼が鈍物として歯牙にもかけなかった連中がぬくぬくとサラリィを獲得し、その生活になんの不足もないことが、自らを天下の才子と自認するたぬの自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。
そうして、たぬき山でしばしば逼塞の日々を送った。
手前、落伍者にて候
いくばくか、困窮の生活を送ったのち、たぬは遂に発狂した。
ちょうど手元不如意にて、という言い訳が効かなくなった頃だった。
或夜半、たぬき山の麓にて酒を喰らい、グースカ寝ているかと思ったら寝台から飛び起き、もんどりうって強かに頭を打ったらしい。
よほどに打ちどころは悪かったと見え、何事か訳のわからぬことを叫びながらたぬき山の山頂の方へと、走り去って行ったらしい。
「クソ記事! クソ記事! クソきじいぃぃぃ……っ!」
絶叫は遥か彼方に木霊し、森に住まう森羅万象の安眠を妨害したという。
尚、行方を追うものは一切おらず、今日に至るまでその消息は不明である。
「その声は、我が友……我が友?」

翌年、大八島からちゅぎというものが務めのため、筑紫州のたぬき山に立ち寄った。麓の宿で行脚疲れを癒すため、束の間の休息を取った。
命を受け、公に奉ずるものの面には、疲れこそ見えたものの充足していた。
一泊の後、公務のため夜明け前に出立の支度を整えていると、宿の主人が血相を変えて、翻意を願い出た。
「お役人様、出立は暫しお待ちになられた方がよろしいかと」
ちゅぎは、あれほど良くしてくれた主人の変わりようを不審に思い、訊ねた。
「はわ! 主人、なにがそんなに駄目なのだね。公務ゆえ、旅路を急ぎたいの」
「へぇ、このたぬき山には化けだぬきが出ますんで……。出立は暁が昇ってからの方がよろしいかと」
主人の諫言は、却ってちゅぎの好奇心に火を付ける類のものであった。
大八島から離れ、地方を歩くとこうした伝説に立ち会えるのを楽しみとしている性分である。
己には恃みとする護衛もあり、腕にも覚えのあることを丁寧に申し伝えた。
結局のところ、一行は暁の出るのを待たず、闇の濃い中に宿を辞した。
無性にその化けだぬきとやらに関心を覚えた。
一行はたぬき山の山脈を越え、街を目指した。
異変を感じたのは、中腹のことであった。ガサリと、風のたたぬ薮が揺らめいたのに、一行は足を止めた。
すわ、熊か狼か。大蛇、虎ということもある。豪胆で知られるちゅぎのこめかみにも冷たい汗が伝うのがわかった。秋口の気温の低きにも関わらず、一行の緊張ゆえか、熱気が宿った。
やがて、藪の中から声がした。
「……あぶないところだった」
いやに低く、苦味のある声だった。唸り声とも、苦悩の声とも判ぜられぬほど低かった。
はた、とその声にちゅぎは心当たりがあった。
「その声はもしや我が友、たぬではあるまいか?」
また唸り声が聞こえた。
「いえ、私はただのアマガエルです」
「いや、たぬなの」
沈黙があり、しばらくして藪の中から再び声が返ぜられた。
「……如何にも。己はたぬである」
苦心惨憺のこもった、苦悩の末搾り出したかのような返事だった。
ちゅぎはたぬの同門として、共に学問に励んだ仲であった。友人の少ないたぬにしては、珍しく仲の良い友と言えた。おそらく、傲岸不遜の塊であるところのたぬの発言を、ちゅぎは聞き流していたからであろう。
不思議と、この両者はぶつかるところがなく、またぶつかりようもなかった。
マグマの如く、独りで怒り泣き狂うたぬの挙動を、柳に風と巧みにやり過ごすちゅぎの能力の賜物であろう。
風にそよぐ枝のように、暖簾を手で押す如くさらりとあしらっていたためである。
ちゅぎは恐怖を忘れ、偶さかの再会を歓んだ。二人はしばしの間、久闊を敍した。そして、なぜ薮からでてきてはくれぬのだと問うた。
たぬの声が答えて言う。
「たぬきに……たぬきになってしまったんだよぉ」
咽び泣く声が、薮の中から聞こえた。きっと、声の主はその双眸から滂沱の涙を流しているに違いなかった。
どうして、この毛むくじゃらで、もふもふの身を友の前にむざむざと晒せようか。今のたぬは、綿埃よりもふもふなのだ。かつ、この身をお目にかければきっと君に、畏怖倦厭の情を起こさせるだろうとも。
「しかし、この身になって初めて人と言葉を交わしたの」
薮の中の声は、会話を懇願した。曰く、たぬきとなって一年。
周りは猿か、鹿か。畜生の類が人語を解すはずもなく、かといって人里に姿を現すわけにもいかず、この事態に行きあって爾来、山に籠っていたという。会話を交わすことに吝かならず。ちゅぎは応じた。
ちゅぎとたぬは、かつての間柄のように会話を楽しんだ。
カレーライス店の秘伝スパイス、最新の学説、経済の動向、ちゅぎの出世、それに対するたぬの賛辞。話題は尽きることなく、重く苦しい雰囲気は霧消し、笑い声すら響いた。
ひとしきり訪れた僥倖を楽しみ、たぬが文明人としての自尊心を取り戻した時、ちゅぎは異類の身となった由来を訊ねた。
ナルキッソスが嫉妬して

たぬは訥々と語り始めた。
職を辞したのち、たぬき山の麓の宿に逗留し文士の真似事をしていたこと。
しかし、相も変わらず一文字一文と書けなかったこと。
そうして或る夜、強かに酔った。己の書けなさに腹が立ち、鯨飲した夜のこと、寝台から起き上がり、水を飲もうとしたところ、足元がおぼつかず倒れ頭を打ったこと。次に目を覚ましたらこの姿になっていたこと。
山中の川を覗き込むと、水面にたぬきの姿が映った。それを己だと認識するまでにはしばらく時間を要した。最初は驚き、慌てふためいた。
しばらくすると、千変万化次々と姿を変じることができた。
茶釜、達磨、虎や山にだって化けることができた。化けだぬきの妖力だろう。自由自在に姿を変ずるうちに、己はなぜ人であったのだろうと考えた。
これは恐ろしいことだ。悍ましいことだ。
己は未だ、完成せぬ己が作品に懸想しているうちに遂に狂ってしまったのだと思った。
さきほど、挙げた対象は丁度己が手帖に書き留めた単語なのさ。ついぞ完成させることのできなかった作品のな。文士を自称しながら、天下第一の文士を名乗りながら、己が作は一つとしてない。己の生は夢物語だったのだ。
文士と名乗ることすら烏滸がましい、哀れな畜生が見る自己満足の夢だったのだ。
思えば、畜生の身となりながら、人語を解するなぞ、おかしな話だ。
己は最初から化けだぬきであり、偶さか人に化けていたのに過ぎないのではないか。
最近ではそう考えるようになった。
事実、最近では無意識のうち様々なものに化け、疑問を感じることは無くなった。
ついこの間なぞ、一晩中山に化けて、何も苦を感じなかったのだ。
人であったたぬよりも化けだぬきとしての生が当然であるという意識が浮かんできているのだ。人であった時間は最早お終いなのだ。
薮の中の声は自嘲気味に嘲笑して見せたかと思うと、沈黙した。
一行はこの夢半ばの文士の困窮を嘆じた。
辺りは次第に白々とし、暁の近きを間近に感じさせた。
「もうここへきてはならねーの」
人が来る時化けだぬきが現れ、たぬが来る時に人はいないのだから。
しかし、今ひとつだけ希いが叶うならば、数行の文章を君が胸に留めてくれぬか。かつて、文士を志した哀れなたぬきが嘯く文章さ。
胸を裂かれ、異類の身に堕ち詩を唄うなどあさましく思うが、君だけでも留めておいてもらえれば、倖せこれに過ぐるものはない。
ちゅぎは、喜んで応じた。部下に命じ一句とも漏らさず書き記させた。
滔々と、たぬは唄った。
あいくるしき このまなこ もふもふ けだまの ぽんぽこ だぬき わがなは たぬ きみの ひとみに ちえつくめいと 薮の中から聞こえてきた唄
「…………」
時に残月、ちゅぎの眼冷ややかに。
一行の熱気はいつしか白んでいた。
山おろしの風が吹き抜け、薮をざわめかせた。
たぬの独白は続いた。
一行は薮中のたぬきの正気を疑った。
それから後、誦すること数十遍。命じられた部下の困惑、甚だなるとき
暗誦はようやく止んだ。
「思えば、こうなってしまったことに心当たりがないではねーの」
「あ……自覚は……」
ちゅぎは察した。
薮の中から懺悔が聞こえた。
己は己が才覚を信ずるあまり、周囲とディスタンスをとり続けた。
周囲がディスタンスをとったのではない。たぬが周囲からディスタンスをとり続けたのだ。
たぬの純粋な世界が汚染されることを防ぐために。たぬの世界が周囲を飲み込んでしまわぬように。
思えば、それが窮余の策であったのだろう。周囲と安易と交われば周囲の者どもの才能の乏しきが露呈してしまう。ゆえにたぬはディスタンスを図り周囲の者どもを守っていたのだと。
ふむ、こうして話してみて、なるほど。確かに思い当たる節はある。
己が心根の優しさがこうしてたぬきとなってしまった要因やもしれぬ。
一行は黙して、語れることのなきを悟った。
たぬの才覚が、あまりに新しきゆえに。独り次元の違うところにいたゆえに。これ以上、届かざる高みを見続けるのが辛かった。
「君に天壌無窮の繁栄あれかしと願うものである」
ガサリ、音をたて薮の中のたぬきがいう。
別れを告げねばならぬ。かつての傍輩にはたぬは夢半ばで斃れたと言ってくれ。このまま草牟須屍となるのは惜しいが、これも運命だ。
最後にこのまま山を越える時に、もう一度こちらを振り返ってほしい。
巨大な山に化け、君に温情を抱かせぬよう。二度とこちらに来ようと思わぬようにあらんかぎりの妖力でもって化けよう。
ちゅぎは別れを述べ、足早に山頂を目指した。
一行は二度と振り返らず、次の目的地へと急いだ。
途中、なにか獣の鳴き声が聞こえたが気に留めなかった。
「いやー。すっごい自己陶酔のたぬきもいたものなの」
まいった、まいった。がははと一笑に付した。
ちゅぎ一行の鉄板の笑い話として、各地に伝播していった。
後年、たぬき山には流暢に人語を解すたぬきが出るという伝説ができた。
おわりに

本家本元、中島 敦先生の『山月記』はこちらなの!

とっても洗練された文章で、短編だから読みやすいの!
読んでくれてありがとうなのー!
